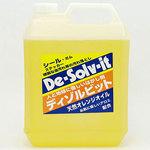
私のnon-toxic 銅版画技法
以前アルチンボルトシリーズ制作中、長い期間の黒ニス止め作業で激しい頭痛に悩まされ、以降、制作と健康面への配慮を考えるようになった。現在教育に携わる者として特に、次世代に有害な製版を引き継がないために、以下、僕なりのnon-toxicへの考え方と、対処法を記す。
欧米の一部ではもはやnon-toxicがあたりまえの国もあれば、また、同じ国でも教育機関や先生によって、全く違う対処法の場合もある。日本でも、大学等の教育機関、または、公私の工房等においても、指導者の考え方で大きく変わっている。これは溶剤使用等への国の規制が緩いことが原因であろう。日本でいま最もnontoxicの先端を実践しているのは、京都の北山銅版画室( http://www.hanga.info/ )であろう。そのホームページには完全non-toxicをベースにした実践が詳しく載っているので、とても貴重なサイトである。また、現在フィンランド在住の作家、石山直司さんのホームページにも(http://www.kolumbus.fi/naoji/ )、彼なりの実践が記されているので参照されたい。
以前non-toxicでは先輩格の石山直司さんの工房を訪ね、いろいろお聞きした際、彼はnon-toxic云々よりもまずクオリティーが大事であると言っていた。当時、なんとかnon-toxicを極めたいと思っていた私は、その言葉に反発したが、あれから研究すればするほどなるほどと思うのだ。ここには記さないが、現在ではすべての銅版画の技法は、non-toxicをベースに可能である。水溶性の樹脂をエアーブラシで拭きつけるアクアチントや、リフトグランド、ソフトグランドなどなど。僕は一通りいろんなWB状の情報を頼りにやっては見たが、まだまだ、古典的な技法と比べると質が低いと思える。(一通りやっただけでは何もわからないが・・・)そして、何より何のためのnon-toxicかということ。環境面、健康被害に問題がなければあえて低い質のモノを求める必然性はないのである。
ではnon-toxic(無毒製版方法)とは何か?何のためか?
1つは環境面、もうひとつは人体への影響、この2つが柱である。
環境面から考えれば、従来の古典的銅版画の製版方法で全く問題がない。むしろ、現在行われているnon-toxicをベースにしたやり方のほうが、ややもすると難があると言える。たとえば水溶性インク。これは少しの石鹸と水でインクが洗浄できるので、従来の石油系溶剤が必要でなく大変便利である。版面、アクリル系のインクを排水で垂れ流すことになる。従来の油性インクは水で流せないので溶剤で洗浄しウエスに吸わせたのは燃えるごみで焼却される。どう見てもこちらのほうが環境に優しい。
次に人体への影響では、古典的製版方法のもっとも有害なのは腐食液に硝酸を使用することだ。硝酸のきわめて有害なことは、過去の事例から明らかなので、多くの工房に硝酸の使用を控えるようにお願いしたい。(ただし完璧な排気設備がある場合や屋外の場合は例外)塩化第二鉄を使えば済むことである。僕は運よく硝酸で製版した経験がなく、硝酸独特の線の味とかアクアチントの質感とか、どうしても硝酸を使いたい人の気持ちがわからないのだが、友人の経験や過去の作家の症状を垣間見たりするにつけ、大学で銅板を習ったときに、最初から塩化第二鉄で製版してきた事は運が良かったと思う。自分だけの工房でずっと制作していくのなら、自分の体が害を受けるだけなのでそれでかまわなければいいのですが。。。。
次は溶剤の問題である。現在はシンナーをグランドやインクの洗浄に使用する人はいないであろう。僕はトナー粉の剥離のときなど、きわめて限定された機会で使用するが、数滴の使用の際も、換気や屋外で行う等の必要を感じる。同様にベンジンやホワイトガソリンなどは、マジックと混ぜて特殊なマチエールを作るなどに使用するが、工房で使用する際は換気設備のある部屋や、通気を充分心掛けないと多くの他の使用者に害を与える。ただし、このような特殊な技法の際に使用する有機溶剤は、僕は全面排除する立場をとらない。
僕が強く主張したいのは実はこれから記すことだ。リグロインについては、含有されるトルエンが有機溶剤として高い毒性を持つことから、溶剤として使用することは避ける必要がある。そしてそれは実は簡単に実行できる。もしあなたが(あるいは工房が)グランドの剥離、インクや油性分の洗浄にリグロインを使用していたら、今すぐ中止して以下の方法をお勧めする。僕は現在(2012,3月)までは、油性分の剥離にエコウォッシュという植物油系洗浄剤を使用して重宝していたが、最近スイスから輸入がされなくなったようで、代用品としてオレンジの皮から抽出して作られたアメリカから輸入されているDesolv-it (ディゾルビット)1ガロン3785ml 6930円 (http://item.rakuten.co.jp/interiortool/desolvit-1g/ )が良い。だだし少し高価である。使用方法は、Desolv-itを少量、油性分に付けてティッシュ等で拭き、完全に拭きとらずに乾燥させずにヌルヌルした状態のときに、上から中性洗剤(水と1:1で混ぜたもの)をふりかけ、ブラッシングすると、完璧に油性分は水で流すことができる。(あまり油性分の残りが多いと環境的に問題はありそうだが・・・)ぜひ、この洗浄方法を試してください。ティッシュ1枚で洗浄できます!!!
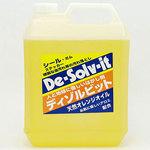
グランド塗布は、固形グランドをウォーマーで熱して溶かし塗布する方法がよい。ゴムローラーで均一に伸ばせば失敗もないではないか。ただ、熱して広げる塗布方法は、経験上流し引きよりは固着が弱いようだ。ピンホールもできやすい。しかし、塗布前に版を腐食液にくぐらせてから醤油で洗うことで格段にグランドの固着が増し、流し引きに匹敵するのだ。次に油煙を付けるなど好みで良いだろう。版面を曇りガラスのように微量に荒らすので、エッチング腐蝕の後、グランド剥離の際にピカールで磨くと元に戻る。液体グランドを流し引きする方法では(ほとんどの指導者はそのように教えているだろうが)はリグロインの害から解放されない。余談だが、ウォーマーは版画用のものは高価なので、「クリスタルウォーマー」というスープなどの保温用の家電製品が、ヤフオクなどで3000円以内で購入できるのでお勧めしたい。
次にニス止めについて。従来は黒ニスをリグロインで溶きながらカバー面に塗布する方法が一般的であろう。ただ、当然ニス止めの間ずっとごく至近距離でリグロインを吸引しなければこの作業は行えない。きわめて危険な工程である。どうしてもこの方法にこだわるなら、そして自分ひとりの工房なら、有機溶剤用のマスクの着用が不可欠である。だが、マスクしての呼吸は結構きついのだ。リグロインは揮発が早く、塗布した黒ニスがすぐ乾いてくれるなどの扱いやすさは、1番かもしれない。しかし、まず、どうしてもこの方法でないとカバーできないかというと実は、他にもいくつかの選択肢があり、かつ人体に無害である。以下、状況によって使い分けるとよい。
1、水性グランド(文房堂製)の使用
これはもともと水性グランドとして開発されたのだが、僕は止めニスとして使う。腐食液には耐えるが水に流れるという性質から、1回だけの腐蝕のアクアチントには最適である。工夫すれば、1回腐蝕後、水で洗わずにティッシュで腐蝕液を拭いてから再びニス止め等当然可能だ。人体には完全無害であり塗りやすい。
2、マジック(溶液)の使用
グランド描画の間違った線やピンホール、プレートマークのカバーにはマジック(溶液)が手軽でお勧めだ。アクアチントの際のカバーにも当然有効で、当然水で洗っても流れないので段階的な腐蝕ニス止めもOKである。剥離は燃料用アルコールやワックス剥がし液を使う。ただし、染料の感度が強いのか手袋をしないと指が真っ黒に染まったり、腐蝕の線がやや黒く染まることが見られる。また、マジック溶液やアルコールに含まれるメタノールは、トルエンなどと比べると数段危険度は低いとはいえ、多くの吸引は有害である。マジックは便利だが、若干有害。それをどの程度許容するかは個人の判断に任せる。
3、乾燥黒ニスを無臭筆洗油で溶きながら使用
無臭の筆洗油は、揮発が緩やかで、それで固まった黒ニスを溶こうというわけだ。無臭の筆洗油は従来の筆洗油から有機溶剤分を軽減したものとされているが、有機溶剤分がゼロでなく、どの程度含有されるのかは表示されていないので、どの程度有害か無害かの判断が難しい。さらに無臭なので考えようによってはより危険かもしれない。僕はどうしても黒ニスを使用したいときこの方法を取っている。どうしても黒ニスを使いたいときとは、アクアチントを腐蝕のたびに松やにを散布し直して、重厚な黒面を作るとき、そのときだけである。筆洗油は揮発が遅いので黒ニスもゆるやかに流れ、リグロイン使用のときよりも逆にカバーしやすいようだ。塗布後ウォーマー等で数分熱すれば固形化して問題ない。
現在のnon-toxicで使う水性の止めニスは、多く塗るとひび割れたり、また、剥離に専用の溶液を作ったり、剥離が容易でなかったりなど、いくつかの問題点がある。
ところで、ワックス等の水性グランドの使用は、まだまだ、古典的な油性グランドのクオリティーには及ばないし、僕の行っている油性の固形グランドを塗布する方法では、人体に害がないので、そもそも水性グランドを使う必然性がない。
ただしこのやり方は特に銅版画制作で有効な方法である。他版種では実践が難しい面もある。
最初に記したが、完璧なnon-toxicはあまり興味がない。簡単にいえばリグロインが嫌いなだけのだ。また、銅版画に錬金術のような怪しい身体に悪そうな雰囲気を求めるならば、僕の意見は無視してください。
2012年1月
作田富幸